二日前の夕方にとんぼが沢山群れをなして同一方向だったと思いますが、飛んでいる様を見ました。
この風景は今までみたことがなかったと思う。
とんぼたちは水平にまっすぐ早いスピードで飛んで、どこかへ群れで移動している様子です。
とんぼは鎧兜などに利用され、五月人形でも見かけることができます。
『勝ち虫』と言われるように前進のみを常なす戦国武将たちが好み、兜の前立て、刀の鍔などに用いました。
(岩槻工業団地内)
赤ちゃん授乳室完備
二日前の夕方にとんぼが沢山群れをなして同一方向だったと思いますが、飛んでいる様を見ました。
この風景は今までみたことがなかったと思う。
とんぼたちは水平にまっすぐ早いスピードで飛んで、どこかへ群れで移動している様子です。
『勝ち虫』と言われるように前進のみを常なす戦国武将たちが好み、兜の前立て、刀の鍔などに用いました。
九月の草花の萩
万葉集にも詠まれている秋の七草の一つ
薄・萩・女郎花・葛・撫子・桔梗・藤袴
撮影をした場所はやや日陰気味のところにより少し遅れ気味でこれからが見ごろです。
紅紫の可愛いお花をいっぱい咲かせます。
お彼岸にはぼた餅・おはぎをお供えいたします。
秋の彼岸のお供え物はおはぎです。
秋に咲く萩の花にちなんでおはぎと呼びます。
山形 立石寺 秋明菊(しゅうめいぎく)
春のお彼岸同様、お墓参りをするなど、ご先祖様に感謝をし、供養をささげる大切な仏教行事です。
昼と夜の長さがだいたい同じとなる秋分の日(九月二十三日)を中心として、その前後三日ずつ合わせる七日間を『秋の彼岸』といいます。
仏教の世界には『西方浄土(西の方角には苦しみのない世界=極楽浄土の世界)があると考えていました。
私たちは御先祖さまを偲ぶ尊い機会です。
私も『ありがとうございます。』と心からお唱えさせていただきます。
『後の更衣(のちのころもがえ)』は『後の衣替え』が今では分かり易い言葉です。
今は衣替えは年に二回、六月一日と十月一日に行います。
今では、その綿入れに代えて厚手のものを用意いたします。
『暑さ寒さも彼岸まで』と申しますが、暑さもおさまります。
このSilver weekは衣の入れ替えをしようと思います。
東北の秋の風景とっても面白い変わった『案山子のコンクールの様子
田んぼにはカラスをよく見かけます。
◆ 童謡 『案山子』
山田の中の 一本足の案山子
天気のよいのに 蓑笠着けて
朝から晩まで ただ立ちどほし
歩けないのか 山田の案山子
山田の中の 一本足の案山子
弓矢で威して 力んで居れど
やまでは烏が かあかと笑う
耳が無いのか 山田の案山子
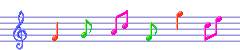
是非!!ご活用くださいますようご案内申し上げます。
多くの方に 『お食い初め祝い膳』はご利用いただいていることとても嬉しく思います。
このたびは、 『お食い初め祝い膳』のおもてなしの料理があると~。良いんですが.....。 と言うご要望にお応えしての料理をご用意させていただいてます。
お孫様のご成長を喜んで下さるご両親をお迎えします。
ママの手作りでおもてなし料理を心を込めて作ります。
小木人形のお子さま行事の料理をご利用ください。
 お子さまが健やの健やかな成長を願うためいろいろお子さまには祝い事がございます。
お子さまが健やの健やかな成長を願うためいろいろお子さまには祝い事がございます。お子様のお祝い事 –お宮参り・初節句・お箸ぞろえ–
★ お宮参り
お子様が生まれて初めて産土神(うぶすまかみ)におまいりする行事です。
お子様がこれから住む土地の氏神様におまいりするのが本来です。
お参りする日、は地方によって違い、生後五十日とか百日目というところもあります。
最近は三十日目頃に行われるのが、多いようです。
★ 初節句 雛人形・五月人形
赤ちゃんが生まれて初めてのお節句の日の祝いで、
古くからの日本の伝統行事です。
赤ちゃんの生まれ月によって、次の年に繰り延べることも多いです。
女の子の場合12月~3月2日までに生まれた場合、一年遅れでお祝いをされても差し支えはありません。
男の子の場合は2月~5月4日までに生まれた場合には、やはり一年遅れでお祝いをされても差し支えはありません。
つまり赤ちゃんが生まれて3ヶ月が目安となります。
★ お箸ぞろえ
生まれて百日目、地方によっては百十日目か百二十日目に祝う行事で『この子が一生食べ物に困らないように』という願いが籠めらた儀式です。
『お食い初め』とも言います。
お祝いに使う食器は新しく整えます。
お子様のお祝い事 –お宮参り・初節句・お箸ぞろえ–
★ お宮参り
お子様が生まれて初めて産土神(うぶすまかみ)におまいりする行事です。
お子様がこれから住む土地の氏神様におまいりするのが本来です。
お参りする日、は地方によって違い、生後五十日とか百日目というところもあります。
最近は三十日目頃に行われるのが、多いようです。
★ 初節句 雛人形・五月人形
赤ちゃんが生まれて初めてのお節句の日の祝いで、
古くからの日本の伝統行事です。
赤ちゃんの生まれ月によって、次の年に繰り延べることも多いです。
女の子の場合12月~3月2日までに生まれた場合、一年遅れでお祝いをされても差し支えはありません。
男の子の場合は2月~5月4日までに生まれた場合には、やはり一年遅れでお祝いをされても差し支えはありません。
つまり赤ちゃんが生まれて3ヶ月が目安となります。
★ お箸ぞろえ
生まれて百日目、地方によっては百十日目か百二十日目に祝う行事で『この子が一生食べ物に困らないように』という願いが籠めらた儀式です。
『お食い初め』とも言います。
お祝いに使う食器は新しく整えます。
お子様のお祝い事 –お宮参り・初節句・お箸ぞろえ–
★ お宮参り
お子様が生まれて初めて産土神(うぶすまかみ)におまいりする行事です。
お子様がこれから住む土地の氏神様におまいりするのが本来です。
お参りする日、は地方によって違い、生後五十日とか百日目というところもあります。
最近は三十日目頃に行われるのが、多いようです。
★ 初節句 雛人形・五月人形
赤ちゃんが生まれて初めてのお節句の日の祝いで、
古くからの日本の伝統行事です。
赤ちゃんの生まれ月によって、次の年に繰り延べることも多いです。
女の子の場合12月~3月2日までに生まれた場合、一年遅れでお祝いをされても差し支えはありません。
男の子の場合は2月~5月4日までに生まれた場合には、やはり一年遅れでお祝いをされても差し支えはありません。
つまり赤ちゃんが生まれて3ヶ月が目安となります。
★ お箸ぞろえ
生まれて百日目、地方によっては百十日目か百二十日目に祝う行事で『この子が一生食べ物に困らないように』という願いが籠めらた儀式です。
『お食い初め』とも言います。
お祝いに使う食器は新しく整えます。
九月の花 真紅に咲き誇るヒガンバナ(曼珠沙華)
『曼珠沙華』は梵語では天上に咲くという花の意味。
『暑さ、寒さも彼岸まで』と言われていますが、秋の夜長を楽しむ頃となりました。
九月二十三日に中日の秋分がやってきます。
その前後七日間が秋の彼岸となります。
また近くではじっとして翅(はね)を休める秋の蝶を見かけました。
その姿には何となく秋の深まりを感じます。
2015年 敬老の日は9月21日
もともとは9月15日でしたが、今では9月第3月曜日となりました。
老人を敬愛し、長寿を祝う日として1966年(昭和41年)に国民の祝日となりました。
聖徳太子によって、身寄りのない老人のための施設『悲田院(ひでんいん)』がこの日に建てられたという由来があります。
なかなか日頃は祖父母、ご両親様には感謝を伝えられないでいらっしゃると存じますが、この日には有難い気持ちをしっかりお届けしたいものです。