「ひいな遊び」と結びつき「ひな祭り」になり、お子さまの健やかな成長と幸せを祈ります。
- おひなさまだけを豪華に飾った親王飾りの雛人形。
- 軽く、移動も簡単、直置きが出来て楽々飾り付けの親王飾り。
- 雛人形を高床焼桐台でコンパクト飾りにまとめました。
- 飾り付け・お片付け・お手入れは簡単と好評です。
羽子板・破魔弓:令和5年11月1日~12月29日 (期間中は無休で営業いたします。)
ひな人形:令和5年11月1日~令和6年2月24日
羽子板・破魔弓:令和5年11月1日~12月29日 (期間中は無休で営業いたします。)
ひな人形:令和5年11月1日~令和6年2月24日
優雅な姿で舞い遊ぶ蝶も形が整った文様で左右対称に組み合わせた『向蝶丸文』上下左右に四羽の蝶が配された『臥蝶の丸』
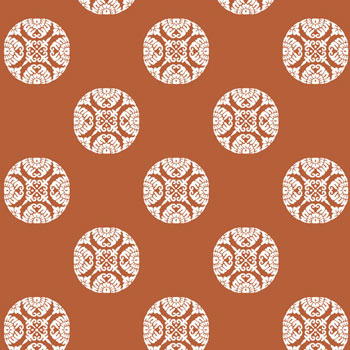

【商品番号】京十番焼桐平台親王飾り
No1014C
【サイズ】間口80cm×奥行45cm×高さ48cm



羽子板・破魔弓:令和5年11月1日~12月29日 (期間中は無休で営業いたします。)
ひな人形:令和5年11月1日~令和6年2月24日
初節句のお祝いは縁起の良い物を集めた文様はいかがでしょうか。
お宝ということから吉祥文様で、「宝珠、打出の小槌、七宝花輪違い、丁字、宝鑰、金嚢・巾着、宝巻・巻軸、熨斗、分銅、隠れ蓑」これらの文様を好みに集めてアレンジします。
もとは密教法具の一つ。
先にとがった珠で火焔が燃え上がることもある。
望みのものを出すことができる珠。
振れば欲しい物が手に入り、望みが叶うという小槌。
物を打つことから敵を「打つ」に通じて吉祥文の一つになった。
スパイスのグローブのこと。
平安時代に輸入され、薬用・香料・染料・丁字油にもなり、希少価値から宝尽くしの一つになった。
蔵を開ける鍵で、雷文形に曲がっている。
縁起の良い福徳の象徴。
お守りやお金、香料を入れる袋で、緞子や錦で美しく作られた。
ありがたいお経の巻物。
交差して置いた物を「祇園守」という。
物の重さを量る時に使うおもり、金銀で鋳で非常時に備えた。
物の目方を計る分銅は弧状にくびれた形が文様として面白いと好まれ縁起の良い物としている。
延壽の象徴。
方勝(ほうしょう)雑ハ宝の一つで菱形を赤や桃色の紐で結ぶ。
天狗が持っているとの伝えがある。
危険な事象から身を隠して護っていただける。
着ると他人から姿が見えなくなる蓑。
宝巻などを入れる筒。
縁起の良い物を寄せ集めた文様 == 瑞祥の表徴


【サイズ】間口80cm×奥行70cm×高さ83cm


【サイズ】間口70cm×奥行62cm×高さ69cm
羽子板・破魔弓:令和5年11月1日~12月29日 (期間中は無休で営業いたします。)
ひな人形:令和5年11月1日~令和6年2月24日
鶴は千年、亀は万年とよく言われて、鶴と亀は長寿の象徴
松の葉をくわえて飛ぶ姿の『松喰鶴』、羽を左右に広げた『鶴の丸』、飛雲の間に飛翔する鶴を組み合わせた『雲鶴』など有職文様として有名。
【サイズ】間口75cm×奥行43cm×高さ41cm
【サイズ】間口60cm×奥行32cm×高さ34cm
【サイズ】間口60cm×奥行32cm×高さ34cm
【サイズ】間口60cm×奥行33cm×高さ35cm
羽子板・破魔弓:令和5年11月1日~12月29日 (期間中は無休で営業いたします。)
ひな人形:令和5年11月1日~令和6年2月24日
飾り物に車の輪をつけ、革所に藻獅子の鹿革染を使用した紫糸威

【サイズ】 間口84cm×奥行45cm×高さ85cm


「神護寺三像」として名高い肖像画 「伝源頼朝像」は「伝平重盛像」「伝藤原光能像」東京国立博物館(上野公園)で只今見られます。

羽子板・破魔弓:令和5年11月1日~12月29日 (期間中は無休で営業いたします。)
ひな人形:令和5年11月1日~令和6年2月24日

栄華を極めた藤原一門を象徴する花である藤は四つ藤丸・八つ藤丸・巴藤など文様化が進み、
平安時代後期、藤原氏繁栄と共に藤は有職文様として発展
飾映えある藤巴文様(藤の花を巴形にした丸い紋)の親王飾り
【商品番号】京十一番親王欅平台飾り
No1009D
【サイズ】間口65cm×奥行37cm×高さ37cm

羽子板・破魔弓:令和5年11月1日~12月29日 (期間中は無休で営業いたします。)
ひな人形:令和5年11月1日~令和6年2月24日
桐竹鳳凰麒麟文様(きりたけほうおうきりんもんよう)
霊長の鳳凰が桐の木に棲み、竹の実を食すとされ、また、霊獣の麒麟 は聖人の出現前に現れ、聖人の出現を告げるものとされる中国の故事 に因んだ吉祥文様である。

【サイズ】間口75cm×奥行43cm×高さ41cm
【サイズ】間口55cm×奥行30cm×高さ31cm
【サイズ】間口60cm×奥行32cm×高さ34cm

【サイズ】間口84cm×奥行45cm×高さ46cm
羽子板・破魔弓:令和5年11月1日~12月29日 (期間中は無休で営業いたします。)
ひな人形:令和5年11月1日~令和6年2月24日

平安時代は上巳の節句の人形は「形代」「撫物」と呼ばれていました。
形代は身代わりの人形で、撫物は人形の身体を撫で、穢れを移すことの呼び名です。
羽子板・破魔弓:令和5年11月1日~12月29日 (期間中は無休で営業いたします。)
ひな人形:令和5年11月1日~令和6年2月24日
以前は貴族や武家などの上流社会や一部の都市の京都だけで行われていました。
「上巳の節句」穢れを人形に託して流し厄落としの行事は次第に貴族の子供の間で行われていた「ひいな遊び」と結びつき「ひな祭り」になりました。
羽子板・破魔弓:令和5年11月1日~12月29日 (期間中は無休で営業いたします。)
ひな人形:令和5年11月1日~令和6年2月24日
お子さまの知識や情操を豊かにする、ひな祭りなどの伝統行事は印象歩かい祭りにしてあげたいですね。
こぼくのひな人形は、お顔やお飾りを自由に選べるので、お子さまに「世界でたったひとつのおひなさま」を贈ることができます。
確かな素材と伝統の技で仕上げられた最高の品質、実際に見ていただければ必ず分かります。

雛人形セットとして平飾り・三段飾り・五段飾り・七段飾り・収納飾り
をご用意しております。
製作工程
① 植物性液体(表面だけでなく表面深まで火が通る液体)を塗ります。
② 酸素バナーで焼きます。
③ 炭取り専用機にてスス炭を取り除きます。
④ 伊保田を塗ります。(ハゼの木に付虫の油を採取し粉末にする、粉米油を液体にしてぬる。)
⑤ 磨き機に掛け磨き艶を出します。
羽子板・破魔弓:令和5年11月1日~12月29日 (期間中は無休で営業いたします。)
ひな人形:令和5年11月1日~令和6年2月24日