日本の文様
宝尽くし (たからづくし)
縁起の良い物を寄せ集めた文様 == 瑞祥の表徴

この宝尽くしは親王・官女の衣装に使われ人気の文様です。
- 宝珠(ほうじゅ)
もとは密教法具の一つ。
先にとがった珠で火焔が燃え上がることもある。
望みのものを出すことができる珠。
- 打出の小槌(うちでのこづち)
振れば欲しい物が手に入り、望みが叶うという小槌。
物を打つことから敵を「打つ」に通じて吉祥文の一つになった。
-
七宝(しっぽう)花輪違い
円の吉祥性か、宝尽くしの一つにかぞえられている。
七宝の円形は円満を表し、吉祥文様。
-
丁字(ちょうじ)
スパイスのグローブのこと。
平安時代に輸入され、薬用・香料・染料・丁字油にもなり、希少価値から宝尽くしの一つになった。
-
宝鑰(ほうやく)
蔵を開ける鍵で、雷文形に曲がっている。
縁起の良い福徳の象徴。
- 金嚢・巾着(きんのう)(きんちゃく)
お守りやお金、香料を入れる袋で、緞子や錦で美しく作られた。
-
宝巻・巻軸(ほうかん・まきじく)
ありがたいお経の巻物。
交差して置いた物を「祇園守」という。
-
分銅(ふんどう)
物の重さを量る時に使うおもり、金銀で鋳で非常時に備えた。
物の目方を計る分銅は弧状にくびれた形が文様として面白いと好まれ縁起の良い物としている。
-
熨斗(のし)
延壽の象徴。
方勝(ほうしょう)雑ハ宝の一つで菱形を赤や桃色の紐で結ぶ。
- 隠れ蓑(かくれみの)
天狗が持っているとの伝えがある。
危険な事象から身を隠して護っていただける。
着ると他人から姿が見えなくなる蓑。
- 筒守(つつもり)
宝巻などを入れる筒。

鱗 (うろこ) 文様
三角形の連続文様を鱗形とか鱗文様と呼ぶ。
鱗文様は大蛇の鱗であり、また龍(水神)の鱗でもある。
江戸時代から鱗文様は女子の厄除け、魔除けの文様として用いられる。
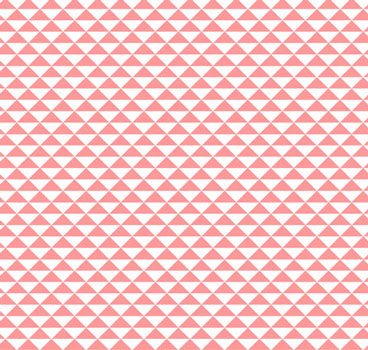
有職文様
平安王朝時代になって公家の装束や調度品に用いられた文様
桐竹鳳凰 (きりたけほうおう)
鳳凰は桐の木に棲み竹の実を食べるとされる事からの文様。
天皇の専用と定められていた。
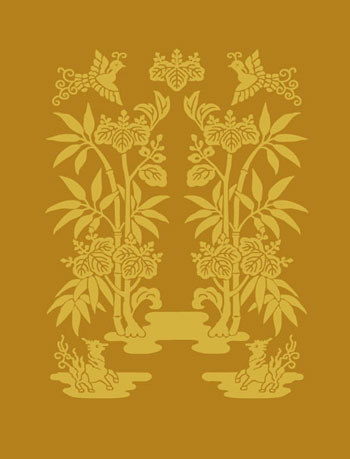
雲鶴 (うんかく)
雲間に飛翔する鶴を表した有職文様の格調の高い文様。
鶴は長寿の象徴です。
貴族社会の装束類に用いられる。

向松喰鶴 (むかいまつくいつる)
松の枝をくわえた鶴。
ペルシャの文様で生まれた花喰鳥(はなくいどり)は真珠の首飾りをくわえることが多く瑞鳥を意味していた。
平安時代に花喰鳥を和風にアレンジしためでたい松と鶴の組み合わせた文様。
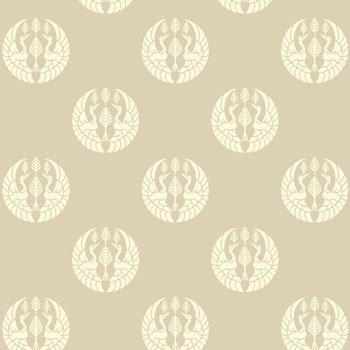
窠中鴛鴦 (かのなかにえんおう)
皇太子は鴛鴦(おしどり)の丸の文様黄丹色の御袍です。
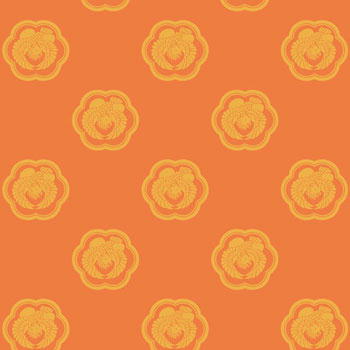
向鸚鵡の丸 (むかいおうむのまる)
夫婦中が良く恒に一緒にいるため、夫婦和合に例えられています。
鸚鵡(おうむ)が和風に変化したもの。
正倉院には仲良く向かい合う鴛鴦の文様が残されています。
現在でも礼・盛装の着物や帯に使われます。
明治期に皇后さまの表着に。
鳥の筆頭には鸚鵡は古くから渡来しており、鳥の筆頭にあげられる。
鳥は こと所のものなれど、鸚鵡、いとあはれなり。
清少納言
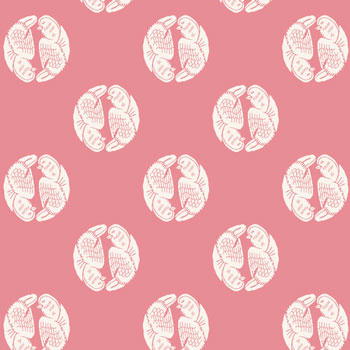
- 臥蝶丸(ふせちょうのまる)
蝶を愛でることは日本は唐から学び、平安時代中期以後に和様化が進み、有職文様の向蝶や臥蝶などようやく蝶を本格的に文様とされた。
四羽の蝶が羽根を広げ、臥せて向かうような文様。
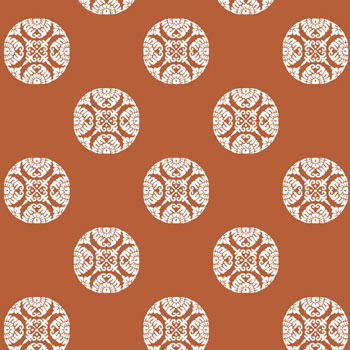
- 向かい蝶丸(むかいちょうまる)
羽根を広げた2匹の蝶で構成された丸文。
多くは浮線文様として女房装束の唐衣なとに用いられた。

唐花丸(からはらのまる)
複雑多弁な花形文様の総称で、形は様々で基本的に円形に構成されている。
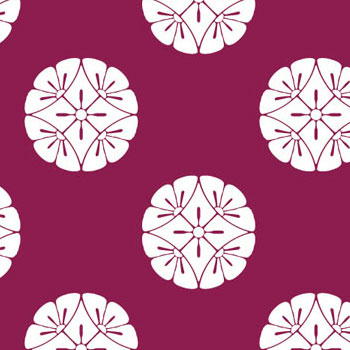
立涌(たてわく)
水蒸気がゆらゆらと立涌いて登って行く様子を文様化したもの。
平安時代以降は膨らみのところに雲や波、藤をを入れた雲立涌・波立涌・藤立涌は有職文様ととて使われる。
- 立涌の中に雲を配する雲立涌

- 立涌の中に藤を配する藤立涌

藤は平安時代後期の藤原氏の盛栄とともに格付けされ、有職文様として装束に使われる。
若松菱(わかまつびし)
松は常緑であることから常磐木と呼ばれ、古くから吉祥文様とされました。
若松を組み合わせて菱形にした文様。

小葵(こあおい)
七宝文から生まれた文様。
円と円の重なる部分を唐草の様な葉で四つの円の接点には小花が円の中央には花文が配してあります。

亀甲文(きっこうもん)
正六角形の幾何学文様はもとは西アジアに起こり中国、朝鮮から日本に伝わった。
日本では亀の甲羅に似ていることからこの名が付き吉祥文様となりました。
平安時代から有職文様として使われる。
亀甲の中が入子になっている文様。
平安時代の公家社会に成立し、現代まで引き継がれ使われている有職文様。
品格の高い鳳凰文や、臥蝶丸文の地文として、重要な役割を持っています。
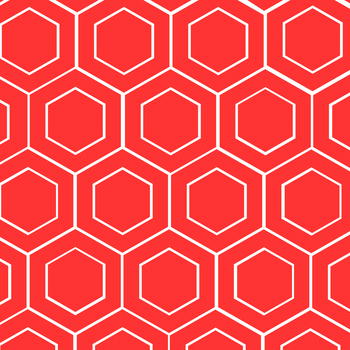
七宝文(しっぽうもん)
大きさの同じ輪を円周の四分の一ずつずらしてできる幾何学的な文様。
七宝文を連続させる、『七宝繋(しっぽうつなぎ)』は
連続性のある文様は慶事が続く、連綿として続いて絶えないという意味のある吉祥文様として好まれ、日頃から良く見かける文様です。
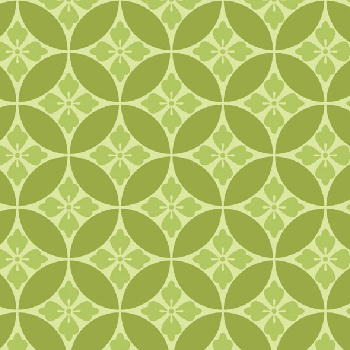
蜀江文(しょっこうもん)
八角形と四角形を繋いだような中に花などの色々な文様が織り出され、この文様は「蜀江錦」と呼んでいます。
連続文様で地文とされずに、精緻で華麗な織物です。
帯などに良く使われます。

青海波
波を図案化した連続文様。
日本では古くは埴輪の着物にも見られるが、水を意味するものとしてえがかれるのは鎌倉時代の古瀬戸瓶子からです。
青海波は数本の同心の半円弧をうろこ上に重ねあわせた幾何学的文様で広々とした大海原の感がします。
海原の情感を湛えた文様。
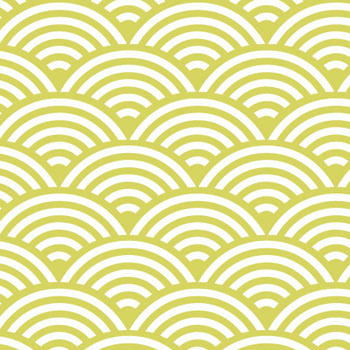
唐草
蔓が四方に巻き付いて伸びる様子は、発展や長寿の象徴として、縁起の良い文様。
絶え続くとして格調高く、礼装用の袋帯などに好んで使われます。
唐草文様の中でも『牡丹唐草』は豪華です。

新着情報

お子様の初節句はママの手作りのお料理 =小木人形 埼玉県 さいたま市 岩槻=
お子さま行事の料理 端午の節句料理ではママの手料理を応援 🎵 武家社会から始まった、男の子の祭りとしての「端午の節句」が庶民に定着したのが、江戸時代の中期です。 鯉のぼりの習慣もこのころか […]

2025年五月人形 戦国武将鎧兜 蒲生氏郷公 =小木人形 埼玉県 さいたま市 岩槻=
岩手県立博物館所蔵模写(鯰尾兜模写) 鎧兜飾り 天下人 織田信長、豊臣秀吉に仕えた戦国名武将蒲生氏郷公 蒲生氏郷具足(燕尾形兜)平台飾り 【商品番号】蒲生氏郷具足(燕尾形兜) 平台飾り […]

2025年五月人形 国宝模写鎧兜飾り 『竹に虎雀 』コンパクト飾り =小木人形 埼玉県 岩槻=
春日大社所蔵 国宝模写 『竹に虎雀』 五分之一 焼桐平台飾り 鎧の大袖には竹に虎雀金物、兜には竹に雀金物のコンパクト鎧飾り 【商品番号】奈良 春日大社所蔵 国宝模写 五分之一 『竹に虎雀』 […]

2025年五月人形 戦国武将鎧兜 陣幕兜飾り=小木人形 埼玉県 さいたま市 岩槻=
飾り方から選ぶ五月人形 戦国武将兜飾りを陣幕飾りでコンパクトに 久能山東照宮蔵 徳川家康の歯朶しだ具足模写兜陣幕飾り 【商品番号】久能山東照宮蔵 徳川家康 歯朶具足模写兜陣幕飾 […]

2025年五月人形 戦国武将鎧兜 本多忠勝公 =小木人形 埼玉県 さいたま市 岩槻=
本多忠勝公 黒糸威二枚胴具足模写 鎧兜飾り 徳川家康四天王の一人、本多平八郎忠勝の鹿の角の前立の鎧は有名です。 勇壮な豪男を誇る戦国武将らしいデザイン。 本多忠勝公鎧 本多隆将氏蔵 黒糸縅二枚胴具足模写 […]




